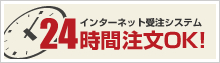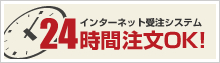基本的には、吸水率が低いほど磁器の性質を現すことから、かつては、吸水率だけで分類されていましたが、最近の製品には、技術発達もあり、吸水が高くても磁器の性質をもつものや、低くても陶器のような性質をもつものがあり、かならずしも吸水率だけで、磁器、陶器、せっ器と判断することは難しくなりました。
磁器質タイル
石英、長石、粘土などを1200〜1350℃で焼成したタイルで、吸水率1%以下のためほとんど水を吸わないタイルです。
素地は緻密で硬く、たたくと清音(金属音)を発します。
耐凍害性や耐摩耗性にも優れているため、外壁タイルや歩行頻度の高い公共の床タイルなどに使われます。
通称で「磁器タイル」と呼ばれる場合もあります。
磁器タイルは、よく焼しめられ、吸水率が低いため、非常に固く汚れにくいというメリットがあります。
無釉で表面に凹凸をつけて滑りにくくした外構用の御影石調タイル等は、歩道や駐車場の床、ビルの外構などに多く採用され、表面を磨いて光沢をもたせた鏡面タイル等は、商業施設などの床などに多数採用されています。
せっ器質タイル
粘土や長石などを1200℃前後で焼成したタイルで、吸水率5%以下のわずかに水を吸うタイルです。
磁器質タイルに比べると吸水性は高いが、素地は硬く、耐候性に優れます。
釉薬をかけず(=無釉タイル)、素焼きの素朴な色むらを生かした地味で自然の風合いの還元焼成の外壁タイルや施釉や無釉の床タイルなどが多い。
「釉薬(ゆうやく)」についてはこちら
陶器質タイル
陶土や石灰などの原料を1000〜1200℃で焼成したタイルで、吸水率22%以下で吸水性の高いタイルです。
素地は多孔質で、たたくと濁音を発します。
土器質 レンガ
800℃前後で焼成し、素地は多孔質で、かなり多く吸水する。
一般的な敷きレンガや積みレンガの他、本物のアンティークレンガを板状に切断加工し、そのやわらかな風合いを活かした壁材のスライスレンガ等があります。